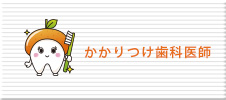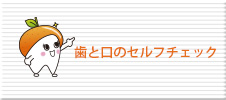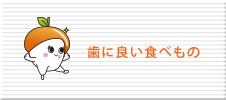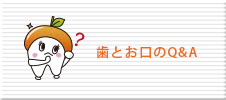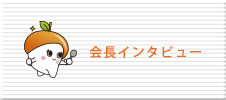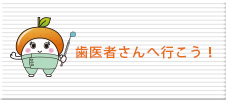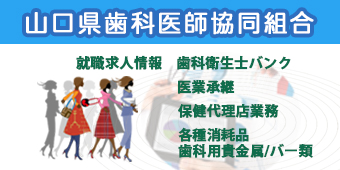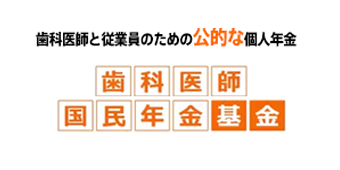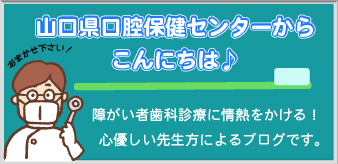『口腔筋機能療法(MFT)で子どもの口腔機能を発達させよう!』
子どもの歯並びは、遺伝だけで決まるわけではありません。実は、舌や唇、頬の筋肉といった「口の周りの筋肉(口腔筋)」の使い方や習慣が、顎の発育や歯の並びに大きく影響しています。例えば、いつも口を開けている「口唇閉鎖不全」や口で呼吸する癖、舌の位置が正しくない、飲み込み方に問題があるといった場合、顎がうまく成長せず、将来的に歯並びが乱れてしまうことがあります。
このような背景を受け、最近では「口腔筋機能療法(MFT)」が注目されています。MFTとは、舌の正しい位置や唇・頬の筋肉の使い方、正しい呼吸や飲み込みの習慣を身に付けるためのトレーニングです。特に成長期の子どもは筋肉や骨の発達が活発なため、この時期に適切なトレーニングを行うことで歯並びや顎の成長を良い方向に導くことができます。
現在では多くの歯科医院で矯正治療と併せてこのMFTを取り入れる取り組みが広がってきています。歯並びを整えるだけでなく、歯並びが悪くなる原因そのものにアプローチすることで治療後の後戻りを防ぎ、長期的に安定した口腔環境をつくることができます。また、見た目の改善だけでなく正しい呼吸や嚥下、発音ができるようになることで全身の健康にも良い影響があるとされています。
「うちの子は大丈夫かな?」と気になったら、早めに歯科医院で相談してみることをお勧めします。早期に気付き予防的にサポートしていくことがお子さまの健やかな成長につながります。
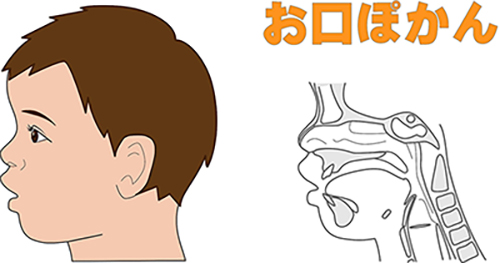
 地域保健委員会 委員 田中 隆之
地域保健委員会 委員 田中 隆之
『むし歯治療の今と昔』
むし歯治療は、時代とともに大きく進化してきました。紀元前3000年ごろの古代エジプトでは、むし歯の痛みに対し蜂蜜やハーブを使った自然療法が行われていたそうです。蜂蜜はその強い抗菌作用から、傷口の保護や感染予防、むし歯にも応用されていたようです。他にも「エーベルス・パピルス」という世界最古の医学書には、痛みを和らげる処置として、ヒヨス(ナス科の薬草)の灰と乳香を混ぜて歯に塗る治療法が記されていて、ヒヨスには知覚まひ作用があり、一時的に痛みが軽減された可能性があるそうです。
日本では、江戸時代に「口中医」が金属製の器具でむし歯を削り、水銀や丁子油などを詰める治療が行われていましたが、麻酔がなく痛みを伴うものだったようです。
明治時代以降、西洋医学の導入により歯科医療は近代化して、手回し式の器具や局所麻酔が登場し、治療の精度と快適性が向上しました。
現在のむし歯治療は、痛みを最小限に抑える技術が進化しています。初期むし歯はフッ素塗布やシーラントで予防的に対応し、中期ではコンポジットレジンなどで修復し、進行したむし歯には根管治療が行われ、電動麻酔やレーザー治療により痛みなど不快感が軽減されています。
さらに、マイクロスコープを使った精密治療や即日修復も登場しています。むし歯は「痛いから治す」から「快適に予防・治療する」時代へと変わっています。人生100年時代、質の高い人生を送るには欠かすことのできないお口の健康のために、歯科医院での定期健診が重要です。
 山口県高等歯科衛生士学院運営委員会 委員、吉本新一郎
山口県高等歯科衛生士学院運営委員会 委員、吉本新一郎
『うがい薬ってどうなの?』
患者さんに洗口液についてよく聞かれます。「うがい薬でうがいをしたら歯磨きしなくていいの?」などです。洗口液を使用する目的は口の中の細菌を減らすことです。細菌はバイオフィルムという膜を作っています。お口の健康を保つために大事なことは、このバイオフィルムを壊すことです。
そのために歯科医院で歯石や、歯の表面の汚れを機械的に除去しています。この状態を維持するために歯ブラシやフロスを正しく用いて歯磨きをしてください。その後、洗口液を使ってうがいを行うと水だけでうがいをするよりも効果的になるという感じです。
しっかり磨いたつもりでも歯科医院で磨き残しを赤く染めてみると、意外と残っていることを経験された方が多いと思います。その磨き残しをゼロにするのは難しいので、歯ブラシの毛先が届かないような深い歯周ポケット内に洗口液を作用させるように使用するので、歯磨きやフロスの補助的なものだと考えてください。
洗口液はいろいろと販売されていて、その成分には口臭予防、むし歯予防、歯垢、歯石の沈着予防、着色除去などありますが、洗口液だけでは口腔内の細菌を減らしたり、歯石を除去したりはできません。口腔内をきれいに保つために、かかりつけの歯科医院を定期的に受診し、歯石や着色などの汚れを除去してもらってください。また正しいブラッシング法を身に付けてお口の健康を維持するようにしてください。ご不明な点はかかりつけの先生にご相談ください。
 広報調査委員会 委員 伊藤昭文
広報調査委員会 委員 伊藤昭文
『お口の健康には機能も必要!』
「8020運動」という言葉を一度は耳にしたことがあると思います。「80歳になっても20本以上自分の歯を保とう」という運動で、2016年の歯科疾患実態調査ではその達成率が50%を超えました。
その一方で、歯が20本あれば満足して食べることができるのかといわれれば、必ずしもそうではないことが分かってきました。歯がたくさん残っているほうが食べやすいのは当然のことですが、それ以外にも舌とお口周りの筋肉が動くことや、唾液がしっかり出ることが重要となってきます。
歯をできるだけ残したり、入れ歯を作ったりしてかめるようにすることはもちろん大切ですが、歯が担うのは口腔機能(お口周りの機能)の一部なので、口腔機能が低下していれば食べたり飲んだりしにくくなる場合があります。
食べ物をかむのはもちろん歯ですが、それだけでは食べることはできません。粘膜や舌で食べ物を動かして、唾液とまぜて歯でかむ、そうしてできた食塊を飲み込む。年を取るにつれて全身の筋肉が低下していく中で、口腔機能だけは低下しないというのは考えにくいことで、舌や飲み込む力も衰えてきます。
こうした口腔機能を維持することは「食べる・しゃべる」といったことに直接関係しているので、QOL(生活の質)の維持・向上にもつながります。口腔機能を検査し管理することで、機能低下を防いだり、低下した機能を回復させたりすることができます。

 学術委員会 委員長 山根 晃一
学術委員会 委員長 山根 晃一
『歯ブラシ選びについて』
歯ブラシは大きく分けて、むし歯を予防するためのものと歯周病を予防するためのものの二つあります。むし歯予防の歯ブラシは、毛先がラウンド型といって丸い形態をしており、歯面の歯垢を効率よく落とすことができます。歯周病予防の歯ブラシは、メーカーにより形態はさまざまですが、毛先が細く加工され歯と歯の間や歯と歯茎の境目の歯垢を除去するのに向いています。
次に、毛の硬さですが、軟らかめで磨くと大体の方は磨いた感じがしないと言われます。実は、私自身が大学時代に行った実験結果では、軟らかめ・硬めどちらの歯ブラシも歯垢除去率の有意差はありませんでした。硬めの歯ブラシは、自身の爽快感(達成感)はありますが、歯ブラシで歯茎を傷つけているかもしれません。また、力を入れすぎると歯を摩耗させ知覚過敏を起こすこともあります。このようなリスクがあるので、特に高齢者や歯茎が腫れている方は軟らかめの歯ブラシが適しています。
では、電動の歯ブラシはどうかというと、大きく分けて音波歯ブラシ・超音波歯ブラシ・電動歯ブラシがあります。それぞれ特性があり、どれも有効なものです。しかし、正しく歯面に当てなければどれを使用しても性能を十分に引き出すことはできません。
どの種類の歯ブラシでも、歯科医院でのブラッシング指導が重要になってきます。自己流の歯磨きは、磨けているつもりが、実は磨けていないことがあるのです。
一人一人歯並びも違いますので、自分に合った歯ブラシと磨き方があります。まずは、歯科医院を受診してブラッシング指導を受けていただき、分からないことは歯科衛生士に相談されることをお勧めします。
 地域保健委員 岩本 潔
地域保健委員 岩本 潔
『お口の健康寿命』
「健康寿命」という言葉をご存じでしょうか? 健康寿命とは心身ともに自立し、日常生活が支障なくできることです。現代の医療は、健康寿命を長くすることを目標としています。以前は、医療とは治療をすることでした。それが早期発見、早期治療となり、未然に病気を防ぐ予防が中心となり、現代では病気にならないだけでなく機能の維持までを目標としています。
歯科医療においても、むし歯や歯周病の治療から定期検診によるメンテナンスへと予防中心の医療へシフトが進んできました。
近年では、口の健康を保つことは人の身体的、精神的、社会的な健康、いわゆるQOL(生活の質)の向上に大きく関与することが分かってきました。そのため歯科の定期検診でも歯の健康はもちろん、年齢に応じた口腔周囲の機能も重視するようになってきています。
小児では歯の萌出時期、顎の発育、かみ合わせ、発音、舌の運動、鼻呼吸の状態など、正常な発育をしているのか、高齢者はかむ力、舌の力、嚥下、発音など、筋力の低下が起きていないか、口腔機能の発育不全や機能低下も評価しています。発育や機能には個人差があり、評価が難しいこともあります。特に機能はゆっくりと低下しますので、自分では気付きにくく、機能低下という線引きも個人差があります。発育や機能の評価は、個人の継時的変化をみる「個人のものさし」と同年代と比較してみる「みんなのものさし」とで判断します。
かかりつけ医を持つことにより、むし歯や歯周病、口腔清掃状態など、今現在の自分の状態と口腔周囲の機能の長期的な評価ができます。定期的なメンテナンスで健康な長寿を目指しましょう。
 学院運営委員会 委員 梶井泰樹
学院運営委員会 委員 梶井泰樹
『口腔内スキャナーの普及について』
歯科治療を受ける際にストレスに感じる、または本当に苦手というものに何があるでしょうか?一般的には麻酔が苦手、歯石を取る際の痛み、染みるのが苦手、歯を削る音、振動が怖い等がありますが、むし歯治療やマウスピース作製のための型取りが本当に苦手、嘔吐反射がすごくて型取りが本当に無理。このような方も日常診療でよく遭遇します。
今日は型取りに関連して、最近普及が進んできた口腔内スキャナーについてお話ししたいと思います。
口腔内スキャナーは、スキャンしたデータを使って歯の詰め物等を作る際や3次元的な診断等に使用します。日本では2005年ごろから導入され始め現在に至りますが、初期は再現の精度がほどほどだったものの最近の製品は従来の高精度の型取りの材料で再現できる程の寸法精度まで性能が向上し、一部の保険診療にも24年から適用されるようにもなりました。しかしまだまだ広く普及しているとは言い難い状況です。
使用実績の積み重ね、性能の向上、コストダウンが実現して、一般的に使用されるようになれば、加齢のため反射が低下し義歯作製の型取りが困難で作製を諦めてきたケース等はもちろん、一般的な診療でも患者さんの型取りストレスからの解放が期待できますので一層の普及を期待したいですね。そんな未来も近いと思います。
 広報調査委員会 委員 吉原正人
広報調査委員会 委員 吉原正人